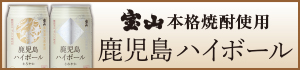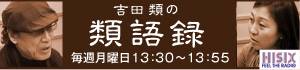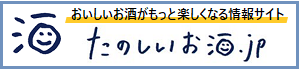〝ホッピー″を味わう会 in 福岡
2009年1月26日月曜日 13:20
1月24日、福岡での〝ホッピー″を味わう会は、なんとボタン雪の舞う中に開催されました。お集まりいただいたメンバーの半数は、ホッピー経験者だったが、専用のホッピージョッキの使用となると、ほとんどが初めて。

焼酎(甲類)、ホッピー、専用ジョッキを冷やし、いわゆる〝三冷の作法″にのっとってドドーっと注げば、全員が見事な泡立てに成功。「カンパーイ」とジョッキを打ち鳴らし合う光景は、どこから見たってビアガーデンのノリだ。そして参加者全員が、本格的なホッピーの飲み口に一杯目で嵌った。さて、後はそれぞれ何杯飲んだやら・・。二次会では、へべれけに近い方もいらしたほどだ。飲みやすく、回りが速いことを、重々ご承知おき下さい。でも、後日の評判は上々。参加者から早くも、九州ウォーカーの編集部へ次会の開催希望メールがぞくぞくと寄せられている。

山口県を含む九州エリアのホッピー待望論は、本物です。
ラベル: ホッピー