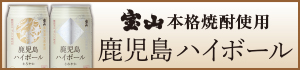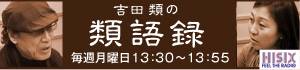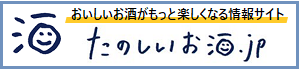霧島・錦灘酒造〜近代焼酎のふるさとを訪ねて その2
2009年8月31日月曜日 1:31

蔵内の一角は試飲とイベント・ホールとなっており、若いスタッフたちが袴姿で控えていた。そのいでたちから察すると、焼酎造りに武道精神を反映させようという試みのようだ。薩摩藩の武の真髄・野太刀自現流(のだちじげんりゅう)の鍛錬法も披露してくれる。薩摩には示現流と表記する剣の流派もあるが、下級武士の実戦剣法として知られていたのは野太刀自現流の方だ。以前、南日本新聞の仕事で取材させてもらったことがある。鍛錬法の一つに、小枝を束ねたて据え置いた横木めがけて、太くて重い特殊な樫棒で打ち下ろしたりする。最初の一太刀で、気合もろとも敵の肩からの袈裟斬りが特徴。正に、この一刀両断は薩摩武士の必殺剣として、幕末の新撰組さえ恐れさせている。


無論、今は質実を重んじる精神修養のために受け継がれた。と、くれば"薩摩自現流"なる銘柄の焼酎がありましたね~。ヤッパリ。しかも、薩摩・島津公が幕府に献上したという米焼酎の一番搾り(花酒)を再現した一品。確かに、立ち上るフルーティーな香りに、歴史ロマンを感じても良いだろう。
「この米、天然農法なんですよ」と、これまた淡々と夫人がおっしゃる。ならばとばかり合鴨農法の水田へ急行した。居るは居るは、棚田ごとに愛くるしい合鴨が・・。


しばらく水田端で合鴨家族の雑草取りを眺めていると、この農法を実践指導する鹿児島大学名誉教授・萬田正治さんがひょっこり現れた。のんびり見える棚田も、水利や合鴨を狙う野生動物など、種々の難問があるらしい。水田管理には科学技術と地道な作業を伴うものの、健康な生活人の温厚さを漂わせる人柄だ。じっくりと、米作りの教えを乞いたいものです。


ひとまず、西日の中に輝く田園風景を残して、今宵の宿、霧島温泉へ向かった。
<お知らせ> 錦灘酒造のご厚意で、10月24日(土曜日)、チェコ村のレストラン「リトル・プラハ」にて、楽しみ俳句会を開催します。ピルスナー、黒豚しゃぶしゃぶなど、飲み、食い放題で、参加費は3000円。俳句初心者でも、問題ありません。問い合わせ先:味香り戦略研究所、担当・小平(こひら)です。電話045-348-7201、ファックス045-333-8121
ラベル: 錦灘酒造






 さらに、土間の奥へと酒造蔵が続くは、続くは・・。地下道を抜けて焼酎蔵へ進めば、瓶入り麦焼酎「天地人物語」(25度)が、出荷用箱詰めの真最中。この麦焼酎がTV・大河ドラマのおかげもあって大人気らしい。
さらに、土間の奥へと酒造蔵が続くは、続くは・・。地下道を抜けて焼酎蔵へ進めば、瓶入り麦焼酎「天地人物語」(25度)が、出荷用箱詰めの真最中。この麦焼酎がTV・大河ドラマのおかげもあって大人気らしい。

 宮崎本店は、古い佇まいの酒造棟があちこちに続いていて、敷地面積の全貌をなかなかつかめない。まずは、応接室にて六代目社長・宮崎由至さんと七代目・ご子息との面談からだ。キンミヤ焼酎との付き合いが古い所為か、初対面の感じがしない。ただ、華美な趣味を排し、質素を旨(むね)とする生活心情の徹底振りには驚いた。後で、美しい社長夫人に伺ったことだが、若い頃の宮崎社長の靴は、たった二足だったらしい。
宮崎本店は、古い佇まいの酒造棟があちこちに続いていて、敷地面積の全貌をなかなかつかめない。まずは、応接室にて六代目社長・宮崎由至さんと七代目・ご子息との面談からだ。キンミヤ焼酎との付き合いが古い所為か、初対面の感じがしない。ただ、華美な趣味を排し、質素を旨(むね)とする生活心情の徹底振りには驚いた。後で、美しい社長夫人に伺ったことだが、若い頃の宮崎社長の靴は、たった二足だったらしい。

 酒蔵の施設も、やはり派手な感じがない。むしろ、古いものを大切に使い込む謙虚な姿勢が清々しく思える。見学の後、蔵の酒「宮の雪」などを試飲させていただくも、キンミヤ焼酎の話題で白熱する。ホッピーとの相性の良さは、味香り戦略研究所のデータでも証明済されている。また、飲み仲間の間では、かねてよりキンミヤ焼酎のラベルの人気が極めて高い。明るいエメラルド色と、金色の亀甲型に縁取られた"宮"のロゴ文字が鮮やかでモダンだ。「ずいぶん昔のことなんで、誰がデザインしたか分からないんですよ」とは、宮崎社長の談。さらに、「宝酒造の大宮久社長とは親友でね。同じ原材料と製法ながら、宝焼酎とは味が違うから面白い、なんて話をしたもんです」と、続けた。無論、味の違いは、水の違いに他ならない。鈴鹿川の伏流水を仕込み水としているが、おそらく伊勢湾に近いこともあって、ミネラル分を含んでいるような気がする。焼津の酒造メーカー「磯自慢」も、同じく海のそばで、すっきり味がウリだ。ドライな口当たりは、ミネラル分を含む硬水の影響が知られている。あれこれと酒談義が弾むも、「そろそろ、話の延長は居酒屋で・・」と、一同の目が輝いた。
酒蔵の施設も、やはり派手な感じがない。むしろ、古いものを大切に使い込む謙虚な姿勢が清々しく思える。見学の後、蔵の酒「宮の雪」などを試飲させていただくも、キンミヤ焼酎の話題で白熱する。ホッピーとの相性の良さは、味香り戦略研究所のデータでも証明済されている。また、飲み仲間の間では、かねてよりキンミヤ焼酎のラベルの人気が極めて高い。明るいエメラルド色と、金色の亀甲型に縁取られた"宮"のロゴ文字が鮮やかでモダンだ。「ずいぶん昔のことなんで、誰がデザインしたか分からないんですよ」とは、宮崎社長の談。さらに、「宝酒造の大宮久社長とは親友でね。同じ原材料と製法ながら、宝焼酎とは味が違うから面白い、なんて話をしたもんです」と、続けた。無論、味の違いは、水の違いに他ならない。鈴鹿川の伏流水を仕込み水としているが、おそらく伊勢湾に近いこともあって、ミネラル分を含んでいるような気がする。焼津の酒造メーカー「磯自慢」も、同じく海のそばで、すっきり味がウリだ。ドライな口当たりは、ミネラル分を含む硬水の影響が知られている。あれこれと酒談義が弾むも、「そろそろ、話の延長は居酒屋で・・」と、一同の目が輝いた。 一軒目、キンミヤ御用達の日本酒場「大感謝」へ、二軒目からは、社長夫人を交えて松坂肉を肉料理「徳寿」にて堪能。取材拒否で有名な店の主も、手を休めて挨拶して下さった。
一軒目、キンミヤ御用達の日本酒場「大感謝」へ、二軒目からは、社長夫人を交えて松坂肉を肉料理「徳寿」にて堪能。取材拒否で有名な店の主も、手を休めて挨拶して下さった。
 三軒目は、四日市名物・一口餃子で有名な中華料理「公園」へ。これほど小粒な餃子は初めて。ビールで流し込む。仕上げは、ワインと創作料理自慢のワインバー「flapper」へ。これが旨くて、白ワインのお代わり、お代わり・・。いいかげんに"お帰り"ってとこで、めでたくお開きとあいなりました。
三軒目は、四日市名物・一口餃子で有名な中華料理「公園」へ。これほど小粒な餃子は初めて。ビールで流し込む。仕上げは、ワインと創作料理自慢のワインバー「flapper」へ。これが旨くて、白ワインのお代わり、お代わり・・。いいかげんに"お帰り"ってとこで、めでたくお開きとあいなりました。 アッ、五軒目に行った「かめ八寿司」を忘れていました。いやいや美味なる旬を、にぎっていただけたのに申し訳ございません。
アッ、五軒目に行った「かめ八寿司」を忘れていました。いやいや美味なる旬を、にぎっていただけたのに申し訳ございません。